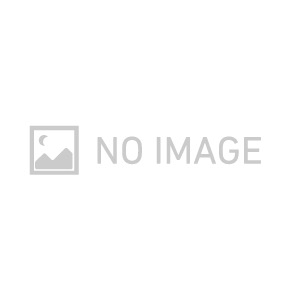雪山登山– category –
-

2401 西穂高岳西尾根
日程: 2024年1月6日(土) - 8(月)山域: 西穂高岳西尾根(北アルプス)参加者: 国府谷・雨宮・他1名行程:第1日目: 新穂高(7:30) - 幕営地2350m(13:45)第2日目: 幕営地(6:00) - 2800m(13:10) - 幕営地(16:30)第3日目: 幕営地(7:30) - 新穂高温泉(13:20) ピーク... -

2312 谷川岳
日程: 2023年12月9日(土) - 10(日)山域: 谷川連邦参加者: 国府谷(L)・雨宮行程:第1日目: 土樽駅(6:10) - 吾作新道 - 万太郎山(12:00) - 稜線幕営(15:00)第2日目: 幕営地(6:20) - 谷川岳(10:10) - 西黒尾根(15:00) 雪山劇場の始まりだー 土樽駅から吾作新道... -

2312 甲斐駒ヶ岳 黒戸尾根
【冬山はじめの黒戸尾根】 日程: 2023年12月2日(土)-12月3日(日)山域: 南アルプス甲斐駒ヶ岳参加者: 国府谷(L)・雨宮・坂田 いつも気が進まないのだが、毎年来ている黒戸尾根。七丈小屋までの道のりが年々辛くなってきたな。なんとか14時半には到着して、... -

2303 爺ヶ岳東尾根
日程: 2023年3月3日(金) - 4日(土)山域: 爺ヶ岳東尾根(北アルプス)参加者: 国府谷(L)・雨宮行程:第1日目: 鹿島村(7:00) - 2000m幕営(11:30)第2日目: 幕営地(5:00) - 爺ヶ岳中峰(7:50) - 駐車場(12:45) 大迫力な爺ヶ岳 大町からも大迫力で聳え立っている爺... -

2302 巻機山
日程: 2023年2月23日(木) - 25日(土)山域: 巻機山(上越)参加者: 国府谷(L)・雨宮・大江行程:第1日目: 清水村(11:40) - 1270m幕営(16:00)第2日目: 幕営地(6:00) - 柄沢山(8:30) - 巻機山(12:50) - 避難小屋上幕営地(14:00)第3日目: 幕営地(6:30) - 登山口(1... -

2212 北岳
日程: 2022年12月28日(水) - 30日(金)山域: 北岳(南アルプス)参加者: 大江(L)・雨宮行程:第1日目: 奈良田駐車場(6:30) - 池山登山口(9:30) - 池山小屋(14:10)第2日目: 池山小屋(4:00) - 北岳(11:00) - 池山小屋(16:30)第3日目: 池山小屋(9:10) - 登山口(10... -

2212 北鎌尾根
日程: 2022年12月28日(水) - 2023年1月2日(日) 前夜発山域: 槍ヶ岳(北アルプス)参加者: 林(L)・江戸行程:第1日目: 自宅(前夜21:30) - みどり湖PA(仮眠)(1:30/4:30) - 新穂高温泉(5:30) - 葛温泉ゲート(8:50/9:20) - 七倉山荘(10:00) - 高瀬ダム(11:00) - ... -

2301 甲斐駒ヶ岳
日程: 2023年1月15日(日)山域: 甲斐駒ヶ岳(南アルプス)参加者: 国府谷(L)・雨宮行程: 駐車場(5:00) - 5合目(11:00) - 駐車場(15:00) 冬トレ甲斐駒ヶ岳黒戸尾根 冬トレーニングに黒戸尾根は外せないので計画。雪も無く快適に登っていったが何故かペースは上... -

2301 赤岳県界尾根
日程: 2023年1月9日(月) 前夜発山域: 赤岳(八ヶ岳)参加者: 国府谷(L)・雨宮行程: サンメドォスキー場(6:30) - 県界尾根 - 赤岳山頂(12:20) - 駐車場(16:50) 日帰り雪遊びと思い県界尾根から真教寺尾根下山で計画。 サンメドゥスキー場駐車場からスタート。... -

2212 白毛門-朝日岳
日程: 2022年12月23日(金) - 24日(土)エリア: 白毛門 - 朝日岳(上越)参加者: 江戸行程:第1日目: 下牧PAにて仮眠(3:30/7:00) - 土合駅(8:00/8:30) - 白毛門(11:50) - 笠ヶ岳(13:40) - 朝日岳(16:20)(1700幕営 - 2130就寝 - 翌0300起床)第2日目: 幕営地発(5:...