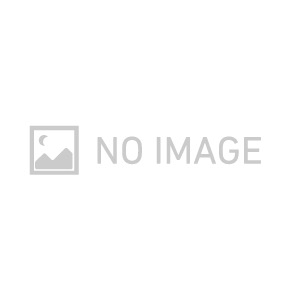2006年山行– category –
-

北鎌尾根、単独トレーニング
日程: 2007年8月25日(土) - 26日(日)山域: 槍ヶ岳北鎌尾根(北アルプス)参加者: 坂田行程: 第1日目: 上高地(6:30) - 横尾(8:10/8:20) - 槍沢ロッジ(9:15/9:30) - 水俣乗越分岐(10:04) - 水俣乗越(10:47) - 北鎌沢出合(12:15) - (ロスタイム) - 北鎌沢二俣(1... -

木曽駒が岳往復 宝剣は途中で断念
日程: 2006年1月14日(日)参加者: 土井(L)・廣岡行程: 本文参照 01:30 菅の台バスセンター駐車場で仮眠。06:30 起床。予報では氷点下15度。車内はバリバリに凍り、車の窓が開かない。エンジンをかけ、ようやく開閉に成功。オニギリも凍っていて食べるのに... -

甲斐駒ケ岳黒戸尾根
期日 : 2006年12月29日~31日(前夜発)メンバー : 清水清二 ・ 塩足京子報告者 : 清水清二 12月28日(木)晴新宿~竹宇駒ケ岳神社60歳過ぎで夜行列車の出発は、シンドイと同時に体にも良くない。28日から冬休みに入れたこともあり、16:00新宿発の列車... -

剱岳早月尾根(偵察山行)
日 時 : 2006年11月3日(金)~4日(土)メンバー: 清水(L) ・ 坂田 ・塩足記 録 : 清水 剱岳早月尾根を正月山行として計画している坂田君の偵察山行に、清水、塩足が行動を伴にする事となった。理由は極めて単純、別山尾根や長次郎谷等は数... -

八海山 ~ 阿寺山
日 時 : 2006年10月28日(土) ~ 29日(月)メンバー: 清水(L) ・ 塩足記 録 : 清水 昨年10月に越後三山(越後駒ケ岳・中ノ岳・八海山)の縦走を行った折、八海山の手前、五竜岳から伸びる緩やかな尾根が続く阿寺山に行くことを考えていた。10... -

有明山
日程:2006年12月23日(土) - 2006年12月24日(日)参加者:芳野(菜)(L)・芳野(達)行程:本文参照記録:芳野(菜) 12月23日(土) 中房温泉へ向かう道のゲートは締まり、手前左に駐車場が設けてあった。今年はとにかく暖冬で、雪は全く無い。 7:50朝寝坊して遅い... -

アイスクライミング阿弥陀岳広河原沢右俣・三叉峰ルンゼ
日程: 2006年12月16日(土) - 2006年12月17日(日)メンバー: 国府谷(L)・廣岡(記録)行程: 文中に記載 今回のアイスクライミングは会山行の八ヶ岳計画の一部として行った。会山行は同時に鵬翔第55期の掛川さんが一年間の海外生活を終えて帰国したそのお祝いを... -

2007年正月山行 甲斐駒・仙丈
日程: 2006年12月29日(金) - 2007年1月2日(火)メンバー: 清水(TL)・塩足(黒戸尾根班) 掛川(L)・飯田・志村・坂本・大和田・掛川(浩/会友)(戸台班)行程: 本文参照 12月29日 「鵬翔1面を飾る」 朝7時に戸台出発の予定だったが、合流に手間取り出... -

2007年正月山行 剱岳(早月尾根)
日程: 2006年12月29日(金) - 2007年1月2日(火)参加者: 平野(L)・坂田行程: 本文参照 冬の剱岳(早月尾根)は入山20日以前に富山県への登山届が必要で、予備日7日間の装備・食糧・燃料を準備する為、事前のトレーニングメニューを含め、気力・体力共に情熱を... -

八ヶ岳、行者小屋テント場に、ケアテント出現、そして大笑いのわけ
谷川岳に続き、八ヶ岳での冬山訓練が行われ、風雪の中私達は、赤岳頂上に上り、他ルートパーテーも無事に帰着、ふもとの鹿の湯に入浴、道の駅で、食事後静岡に帰る掛川夫婦とも別れ、帰京しました。 さて今回は掛川君の一年ぶりの帰国祝いを、時間の都合上...