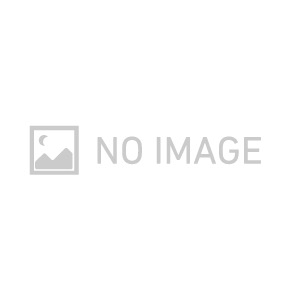2005年山行– category –
-

White christmas at Mt.YATSUGATAKE
阿弥陀岳北稜バリエーション登攀Witer Variation Route of Mt.AMIDADAKE (North ridge)(English version below) 山域:南八ヶ岳(阿弥陀岳)日時:2005年12月23日~2005年12月25日メンバー:坂田、後藤計画: ・12/23 阿弥陀岳北稜登攀 ・12/24 赤岳主稜... -

八ヶ岳広河原沢
日時: 2005年12月17日(土)~2005年12月18日(日) 参加者: 鵬翔山岳会: 坂田・静岡山岳会: 伊東・古川・鈴木 山域: 八ヶ岳広河原沢 形態: アイスクライミング 行程: 第1日目: 舟山十字路~二俣~左俣~10m大滝~中央稜~二俣・第2日目:二俣~ポストクリスマ... -

Winter ! ,Most Beautiful Sesason
谷川岳雪上訓練報告 山域:谷川岳期間:2005/12/17~05/12/18行程 12/17:上野~水上~谷川岳ロープウェイ駅~天神平~熊穴沢出合手前幕営 12/18:幕営地~天神平~谷川岳ロープウェイ駅~上毛高原駅~東京駅参加者:清水(清)、塩足、志村、清水(幸)、後... -

富士山耐寒訓練(敗退)
日時: 2005年12月3日(土)参加者: 坂田(単独)山域: 富士山形態: 耐寒訓練行程: スバルライン~3250mで敗退今シーズンこそはガンガン登るぞ!と気合いの冬。スタートはもちろん富士山での耐寒&耐風訓練。誰も集まらず(涙)。けどスタートで引き下がる訳には... -

雨飾山(1,963m)
2005.11.05(土)~11.06(日)メンバー:(L)清水、飯田、塩足、和内日本海は鈍色を帯び、空から降り注ぐやわらかな光を群青の波先にきらめかせ凪いでいた。海は静かに秋の終わりを告げていた。11月5日(土)10:00、飯田さんと私を乗せたタクシーは親... -

金城山(1,369m)越後巻機山塊
2005年10月22日(土)清水清二、他(引率登山)金城山は標高こそ高くはないが、巻機山から派生した尾根と、その昔上杉家の城山として知られる坂戸山の間に位置し、急な尾根に岩場、鎖場が数箇所あり、頂上岩峰は東側が切り立つっており、地元では昔から八... -

秋の苗場より
苗場山 山行報告平成17年10月15~16日前夜発~和田小屋(かぐらゲレンデ)~苗場山~和田小屋CL 牧田、後藤、志村(志村記)10月15日(土)晴れのち土砂降り18:00 横浜駅集合…ですよね?おーい!おーい! (集合時間になっても誰も来なかったようです。... -

越後三山(魚沼三山)縦走
日時 : 2005年10月8日(土) ~ 10日(月・祝日) 前夜発参加者 : CL清水清二 ・ 飯田平八郎 ・ 塩足京子報告者 : 塩足京子10月7日(金)東京駅20:24発の上越新幹線に各自乗車しての集合であるが、連休前の東京駅は大変なごった返し状態であった。... -

お宿に泊まってクライミング
2005年09月23日(金)~2005年09月24(土)城ヶ崎ファミリークラックエリア フリークライミングメンバー:L坂田、後藤、(鈴木正、鈴木知)、国府谷(記)9月22日 翌日の早出に備えて長津田の鈴木家へ前乗り。立派なリビングで今回の合宿(ツアー)の成功を... -

南八幡平 葛根田川溯行
日時 : 2005年9月17日(土) ~ 19日(月) 前夜発参加者 : CL清水清二・塩足京子報告者 : 塩足京子9月16日(金)東京駅20:04発の東北新幹線に乗車、盛岡駅22:27着。今宵は、ここで仮眠を取る。駅裏の駐輪場に出る人通りの少ない出入口のシャッタ...