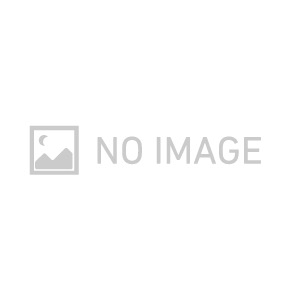2008年山行– category –
-

2008年末合宿
日時: 2008年12月27日(土) - 30日(火) *26日前夜発山域: 八ヶ岳形式: アイスクライミング&バリエーション:定着参加者: 国府谷(L)・掛川・芳野・廣岡・松林・志村・土井行程:第1日目: 美農戸口駐車場(8:30) – 赤岳鉱泉(9:00) – 裏同心ルンゼ(15:05) –... -

阿弥陀岳南稜山行報告
日時: 2009年3月28日(土)山域: 阿弥陀岳南稜(八ヶ岳)参加者: 久世(L)・松林行程: 舟山十字路(6:00) - 旧旭小屋(6:35) - 立場山(9:00) - 無名峰 - 阿弥陀岳山頂(13:30/14:00) - 舟山十字路(17:00) 晴れ後快晴 02:00舟山十字路まで路面に積雪は無く、ゲート... -

タカマタギ山行報告
日程: 2008年2月14日(土) - 15日(日) 前夜発山域: タカマタギ(上越)参加者: 久世(L)・飯田・平井・松林 今年の雪不足を象徴する山行だった。 2月13日 夜 新宿にて、久世・飯田・松林集合。松林さんの車にて、一路土樽駅を目指す。水上の辺りに来ても、ほ... -

大同心大滝
日時: 2009年2月22日(日) 前夜発山域: 大同心大滝(八ヶ岳)形態: アイスクライミング参加者: 国府谷(L)・広岡・土井 今シーズン3回目のアイスは日曜日に夜行日帰りで八ヶ岳へ。土曜日22時すぎに美濃戸口の駐車場に着いてそのまま車中泊。エスティマ... -

尾白川刃渡り沢
日時: 2009年2月1日(日) 前夜発山域: 尾白川刃渡り沢(南アルプス)形態: アイスクライミング参加者: 国府谷(L)・広岡・土井 1月31日(土)の天候が悪く、当初の駒津沢から日帰り可能な刃渡り沢に計画を変更した。中央道韮崎インター下りて20分ほどにある道の... -

甲武信ヶ岳 -冬のはじまり-
日時: 2008年11月29日(土) - 30日(日)山域: 甲武信ヶ岳(奥秩父)形式: 登山(小屋泊)参加者: 志村(L)・他行程:第1日目: 駐車場(8:30) - 徳チャン新道登山口(9:00) - 甲武信小屋(15:05)第2日目: 山頂へ往復(7:10/7:50) - 下山開始(8:00) - 登山口(11:00) - 駐... -

八海山
日時: 2008年11月1日(土) ~ 2日(日)山域: 八海山(上越)参加者: 塩足(L)・坂田・和内行程:第1日目: ロープウエイ山頂駅 - 八海山避難小屋 - 八ッ峰の岩場を空荷で大日岳まで - 八海山避難小屋泊第2日目: 八海山避難小屋 - 五竜岳 - 阿寺山 - 山口へ下山を... -

南アルプス・黒戸尾根
日程: 2008年11月2日(日) - 3日(月)参加者: Y(L)・他1名行程: 本文参照 最近の体力不足は目に余る。高度差2200mを往復する甲斐駒はトレーニングに最適だ。山は、一に体力・二に体力。ひたすら登る事にした。竹宇駒ケ岳神社を6時50分に出発。紅葉はイマイ... -

屏風岩・雲稜ルート
日程: 2008年10月12日(日) - 13日(月)参加者: Y(L)・他1名行程:第1日目: 沢渡駐車場(6:45) - 上高地(7:10) - 横尾(9:20) - T4尾根取り付き(10:40/11:00)- T4(12:30/13:00) - 扇岩テラス(15:00)泊第2日目: 出発(6:45) - 終了(10:20/10:50) - 屏風の頭(12:0... -

白馬鑓ヶ岳・山スキー
日程: 2008年5月17日(土) - 18日(日)参加者: Y(L)・G・他1名行程: 本文参照 5月17日 山スキーをする人がいない、と思っていたら、Gさんがボードで参加したいとの事。仲間がいるのは嬉しいことです。楽しい滑りをしましょう、とメールを返す。 10時には小日...