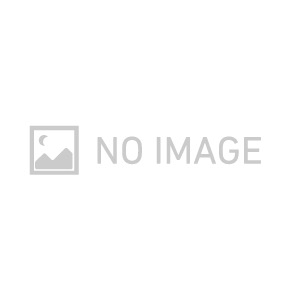2010年山行– category –
-

ぽかぽか青葉
日時: 2010年12月11日(土) - 12日(日) 山域: 青葉(福島県いわき市) 参加者: 国府谷・他2名 タイトルを読んで「語彙が少ないなぁ」とか言わないように。 今年も青葉は暖かかった。 今週末はS木家と青葉。背中痛めてたりで岩場は1月ぶり。 まだ痛いけど無... -

佐武流沢 沢登り
日程: 2010年9月18日(土) - 20日(月) 前夜発山域: 上信越 魚野川支流参加者: 国府谷(L)・斉藤・下島行程: 第1日目: 湯田中(6:00) - 切明温泉(8:00) - 中津川左岸登山道 - 佐武流沢入渓点(11:40) - テンバ到着(14:30)第2日目: テンバ出発(9:00) - 崩壊地経... -

フリーまとめてアップ
「一日一本」 日時: 2010年10月16日(土) - 17日(日)山域: 有笠山(群馬)参加者: 国府谷・坂田・他1名行程: 省 10月16・17日は春以来久しぶりに有笠山であった。S木さんと坂田さんの3人。6時荻窪7時的場岩場9時過ぎ。西口駐車場はクルマ無し。もちろん岩場(... -

谷川岳登攀報告
日程: 2010年9月18日(土)前夜発 - 20日(月)山域: 谷川岳東尾根参加者: 久世(L)・松林・廣岡行程:第1日目: マチガ沢BC - 第1見晴し - シンセン沢 - 左俣 - 東尾根 - トマの耳 - 厳剛新道 - マチガ沢第2日目: 一ノ倉沢出会い - 夏道 - ヒョングリの滝下降地... -

フリーまとめてアップ
日時: 2010年10月2日(土)山域: 天王岩(奥多摩)参加者: 国府谷・坂田行程: 省略 「たまには電車もいい」 最近仕事中に「ワンクッション」と言うところを「ワンテン」と言ってしまう皆さん、こんにちは。随分ひさびさの天王岩は坂田さんと(不満はないけど)。... -

鳴沢岳・赤沢岳・針ノ木岳・蓮華岳縦走報告
日時: 2010年8月27日(金) - 29日(日)山域: 後立山連峰南端 一般路縦走 参加者: 松林(単独)行程:第1日目: 扇沢駐車場(8:10) - 柏原林道 - 種池小屋(13:00)第2日目: 種池小屋(6:50) - 鳴沢岳(9:40) - 赤沢岳(10:45) - スバリ岳(13:10) - 針ノ木岳(1... -

魚野川本流遡行
日程: 2010年7月17(土) - 19日(月)山域: 魚野川本流(上信越)参加者: 国府谷(L)・土井・斉藤・中村行程: 前夜: 新宿駅西口集合(21:30) - 野反湖(駐車場にて泊)第1日目: 切明温泉方面への登山道を行く(6:30) - 11: 10 渋沢ダム着魚野川へ入渓(11:30) - 高沢... -

北岳バットレス山行報告
日時: 2010年6月25日(金) - 26日(土)山域: 北岳バットレスピラミッドフェース - 第四尾根(南アルプス)参加者: 国府谷(L)・松林行程: 前夜: 調布駅(22:00) - 芦安駐車場(車中泊)(1:00)第1日目: 駐車場(5:00) - (乗合タクシー) - 広河原(5:50/6:15) - バット... -

鶏冠谷右俣
日程: 2010年6月20(日)山域: 鶏冠谷右俣(奥秩父)参加者: 中村・土井行程: 西沢渓谷駐車場(8:05) - 東沢下降 - 鶏冠谷出合(8:45) - 魚止ノ滝 - 奥飯盛沢出合 - 3段12m滝 - 20m逆くの字滝 - 二俣(11:30) - 25m大高巻ゴルジュ下降 - 30m滝 - ナメ連続 - 40m滝... -

剱岳八ツ峰主稜縦走
日程: 2010年5月1日(土) - 3日(月)前夜発山域: 剱岳(北アルプス)参加者: 久世(L)・廣岡行程: 第1日目: 扇沢 - 室堂 - 剣御前小屋(別山乗越) - 三田平(幕営) 第2日目: 三田平 - 長次郎谷出合 - 八ツ峰主稜縦走(1・2峰のコル - 八ツ峰の頭 - 池ノ谷乗越)...
12