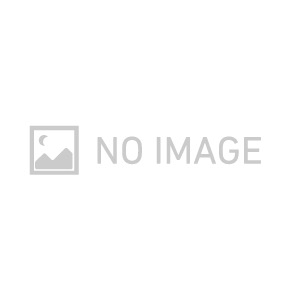2011年山行– category –
-

那須岳山行記録
日程: 2011年12月24日(土) - 25日(日) 山域: 那須岳(北関東) 参加者: 松林・中村 第1日目: 溝の口(6:00)発 - 大丸温泉駐車場(9:30) - 避難小屋(11:30) - 茶臼岳(12:00) - 朝日岳(14:30) - 清水平(15:30) 第2日目: 清水平(7:30) - 中の大倉尾根(9:30)-北温... -

阿弥陀北西稜偵察?
山域: 阿弥陀岳北西稜(八ヶ岳) 日程: 2011年12月18日(日) 参加者: 国府谷(L)・坂田 八ヶ岳もやっと冬らしくなってきたようです。 12月18日は前夜発日帰りで阿弥陀北西稜メンバは坂田さんと二人。 17日20:30に高円寺で土井さんと合流。 土井さんは単独で阿... -

ザイル祭
場所: 氷川キャンプ場(奥多摩) 日程: 2011年11月19日(土) - 20日(日) 参加者: 国府谷(幹事)・久世(想太朗)・飯田・松林・齋藤・下島 今年もザイル祭の時期がやってきた。 いつもはハイキングや岩トレなども併せて実施するのだが、今回は天気予報が芳しくな... -

八ヶ岳
山域: 裏同心ルンゼ・中山尾根(赤岳鉱泉BC) 参加者: 国府谷(L) 坂田 廣岡 日程: 2011年11月26日(土) - 27日(日) 行程: 第1日目: 美濃戸(7:00) - 美濃戸口(8:00) - 赤岳鉱泉着(10:00) - 裏同心ルンゼF1(11:30) - 大同心基部(15:45) - 赤岳鉱泉(17:00) ... -

秋の深南部 前黒法師と大札山から蕎麦粒山紀行
日時: 2011年11月22日(火) - 23日(水)山域: 前黒法師(寸又峡周辺)参加者: 掛川(L)・URAN(会友)行程: 本文参照 紅葉を楽しみに深南部の入口の山に行ってきた。朝静岡市内の家を出て、川根路をたどり順調ならば3時間かからないで登山口の山犬の段につく。静... -

with 静岡山岳会 in 小川山
まずは齋藤さん撮影の写真から(こちら) -

谷川岳登攀報告
(画像入りはこちら) 日時: 2011年9月24日(土)-25日(日) 山域: 谷川岳(一の倉沢2ルンゼ・Bルンゼ) メンバー: 久世(L),松林 行程: 前夜: 荻窪駅南口集合(22:00) - 練馬IC- 水上IC - 谷川岳(23:00) - ロープウェー駐車場(テント泊) 第1日目: 起床(3:30) - 駐... -

笠ヶ岳
日時: 2011年10月4日(火) 山域: 笠ヶ岳(志賀高原) 参加者: 掛川(L)・URAN(会友) 行程: 硯川駐車場(10:30) - 笠ヶ岳山頂(12:30/13:30) - 硯川駐車場(15:30) 10月4日 晴れ 笠ヶ岳は、特異な形をしているので遠くからでもすぐわかる。志賀高原の車道を上がっ... -

中央アルプス 空木岳 (静岡山岳会との合同山行)
日程: 2011年6月4日(土) - 5日(日) 前夜発 山域: 空木岳(中央アルプス) 参加者: 国府谷(L)・飯田・平井・(静岡山岳会より9名) 行程: 前夜: 平井車にて駒ヶ根菅の台駐車場付近にて仮眠(国府谷・平井)・静岡駅にて静岡山岳会会長の車に便乗し駒ヶ根菅の台駐... -

聖岳登山
日時: 2011年7月12日(火) - 14日(木) 山域: 聖岳(南アルプス) 参加者: 掛川(単独) 11日夜静岡を立ち、12日朝長野県側の便ケ島登山口に着きました。 聖光小屋の青木さんに挨拶をして、登山を始めました。 約6時間ほどで聖平小屋に着きました。 小屋は15日か...
12