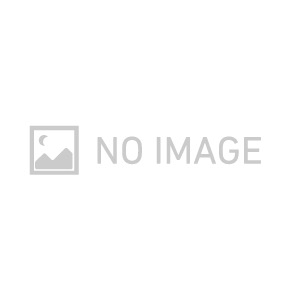2012年山行– category –
-

八ヶ岳赤岳鉱泉B.C(小同心クラック登攀)報告
日時: 2012年12月22日(土) - 24日(月) 前夜発山域: 小同心クラック(八ヶ岳)参加者:国府谷(L)・坂田・松林行程:前夜: 10:00調布駅-01:00小淵沢道の駅(車中泊)第1日目: 坂田合流(7:15) - 美濃戸(9:00)~赤岳鉱泉B.C設営(10:30) - 行者小屋往復(赤岳主稜登攀... -

奥穂高岳コブ尾根登攀
日時: 2012年9月22日(土) - 23日(日)参加者: 久世(L)・松林・廣岡山域: 奥穂高岳コブ尾根(北アルプス)行程: 第1日目: 沢渡 - 上高地 - 岳沢小屋 - コブ沢 - コブ尾根上=幕営第2日目: 幕営地 - コブ - コブ尾根の頭 - 天狗のコル - 岳沢小屋 - 上高地 - 沢... -

土日にて甲斐駒黒戸尾根・三ツ峠
日時: 2012年8月25日(土) - 26日(日)参加者: 久世(L)・平井(26日、和樹君と)・松林(26日)・廣岡山域: 甲斐駒ヶ岳黒戸尾根(南アルプス)・三ツ峠屏風岩行程:第1日目: 竹宇駐車場 - 黒戸尾根 - 甲斐駒ケ岳頂上 - 黒戸尾根 - 竹宇駐車場第2日目: 裏三ツ峠駐車... -

天狗尾根(八ヶ岳)山行報告
日時: 2012年11月24日(土) - 25日(日) 前夜発 山域: 天狗尾根(八ヶ岳) 形態: バリエーション 参加者: 国府谷(L)・坂田・松林・土井 天気 :11/24 11/25 積雪状態: 出合小屋より積雪はあったが、日当りの良い個所は無雪。天狗尾根第2岩稜からアイゼン... -

そろそろ冬支度
日時: 2012年11月11日(日) 山域: 三ツ峠 参加者: 坂田(L)・鈴木 行程: 本文参照 そろそろ今シーズンの冷え込みはどうなるのか、気になる時期。シーズン前のトレーニングとして、三ツ峠へ行ってきた。日曜日は雨の予報。当然ながら土曜日から取り付きたかっ... -

久々の再会
日時: 2012年11月3日(土)山域: 湯河原幕岩参加者: 坂田(L)・丸尾(関西支部)・他1名行程: 本文参照 今回も「久々」なことがあった。関西支部の丸尾さんとの再会である。当初は三つ峠でアイゼントレでもやろうかと思っていたのだが、丸尾さんから伊豆・箱根... -

獅子岩いったよ
日時: 2012年10月28日(土) 前夜発山域: 上州子持山参加者: 国府谷(L)・松林 またまたひさーしぶりの岩場は、なんと子持岩獅子岩。 メンバは松林さんと。声掛けたメンツには全部ふられました。 26日の夜に荻窪で待ち合わせして松林車にて最寄の駐車場まで。... -

中芝新道・谷川馬蹄形登山報告
日時: 2012年10月7日(日) - 8日(月) 前夜発山域:谷川岳参加者: 松林(単独) 行程: 前夜: 自宅(20:30) - 練馬IC - 水上IC - 土合橋駐車場(23:00/車中泊)第1日目: 起床(4:00) - 土合橋駐車場(6:00) - 湯檜曽川新道 - JR見張り小屋(7:00/7:10) - 芝倉沢出合(7:... -

今週もフリー
日時: 2012年10月13日(土)山域: 氷川屏風岩(奥多摩)参加者: 坂田・鈴木行程: 本文参照 久々の奥多摩。フリーに限らず、足を踏み入れたのは数年ぶりかも。やはり遠かった。特に帰りの夜道が。行きは前夜発で待ち合わせ予定だったが、泰が風邪をひいてしまっ... -

雨の幕岩
日時: 2012年10月7日(日)山域: 湯河原幕岩参加者: 坂田・他2名行程: 本文参照 快適な秋の三連休、フリー日帰りというプランはただでさえもったいないのに、なんと夜半から雨。結局昼過ぎまで雨。ようやく雨が上がったところで桃源郷エリアへ向かい、取り付...