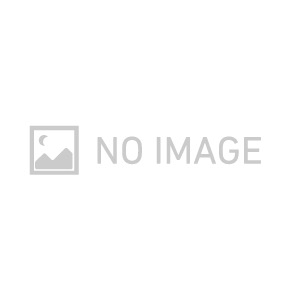2013年山行– category –
-

2013三つ峠クライミング
三つ峠クライミング 日時: 2013年10月12日(土) 山域: 三つ峠 参加者: 久世(L)・五十島 行程: 前夜東京発- 裏三つ峠- 木無山- 天狗岩(ロープワーク練習) - 屏風岩- 裏三つ峠- 帰宅 今回は三つ峠にクライミングへ行ってきました。とは言っても私は全くの初心... -

三つ峠クライミング
日時: 2013年10月12日(土) 参加者: 久世(L)・五十島 引き続き下記の記録も届きました。 「201410mitutouge.pdf」をダウンロード -

北アルプス・蝶ヶ岳-常念岳縦走
日時: 2013年8月17日(土) - 19日(月) 参加者: 久世(L)・五十島 五十島さんより下記記録が届きました。 「201408tyougatake.pdf」をダウンロード -

八ヶ岳縦走
日時: 2013年7月20日(土) - 21日(日)前夜発 山域: 八ヶ岳 参加者: 廣岡(L)・五十島 行程: 前夜発夜行バスにて白駒池6:20到着 第1日目: 白駒池登山口(7:00) - 中山展望台(9:00) - 黒百合ヒュッテ(10:40) - 東天狗岳(12:10) - 根石岳(13:00) - オーレン小屋(... -

秋の懇親山行、箱根外輪山ハイキングの報告
安達さんより記録をいただきました。 そのままPDF形式にしてアップしますので、 「201309konsin.pdf」をダウンロードをクリックしてしてください。 -

上高地アイスクライミング
日時: 2013年3月23日(土) - 24日(日)山域: 上高地周辺(北アルプス)参加者: 国府谷(L)・久世・廣岡 上高地のアイスエリアの存在を昨年知り、時期も3月いっぱいまで楽しめるという事と、坂巻温泉に車を駐車出来る事も判り、是非行きたいと思っていた。私自... -

懇親スキー山行
日時: 2013年3月2日(土) - 3日(日)場所: 菅平スキー場参加者: 安達(幹事)・平井・久世・牧田・平井和樹・久世想太朗・他1名 今年も安達さん幹事にて、菅平にて懇親スキーを行ないました。名古屋から牧田君が参加してくれ、唯一のボーダーとしての参加とな... -

春(夏?)の懇親山行
日時: 2013年6月29日(土) - 30日(日)山域: 箱根周辺(明星ヶ岳・金時山)参加者: 安達(幹事/孫)・南・平井・久世・牧田 今回の懇親山行は、以前企画して台風に阻まれた、箱根強羅に泊まって温泉と山を楽しむをコンセプトにした懇親山行の再トライでした。残... -

2013剣岳
日程: 2013年6月9日(日) - 10日(月) 前夜発山域: 剣岳(北アルプス)参加者: 土井行程:第1日目: 新宿バスターミナル(23:10 高速バス) - 扇沢(4:45/7:30 仮眠) - 室堂(9:45/10:15)-別山乗越(12:45) - 剣御前(14:00) - 剣御前小屋第2日目: 起床(2:50) - 出発(4... -

GW仙丈・甲斐駒記録
日程: 2013年4月26日(金) - 29日(月)山域: 仙丈ヶ岳・甲斐駒ヶ岳(南アルプス)参加者: 中村(L)・土井行程:第1日目: 調布駅(21:00) - 沢渡駐車場(0:30) 小雨、仮眠第2日目: 起床(5:10) - ミゾレで二度寝 - 沢渡(7:15) - 上高地BT(8:10) 大雪のため入山規制、...
12